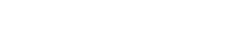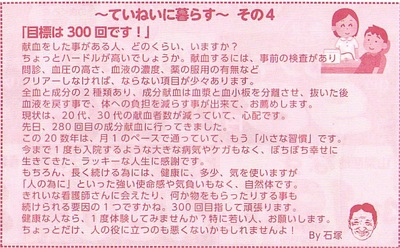料理も食事も楽しんで!
浜松主催の料理教室に通っています。
「浜松ヒューマンセミナー」という社会人対象の学習講座で協働センターで行われています。
9月から11月までの6回コース。
定員20名のところ、男性は2名のみ。女性の中で、
しっかり女子トークにも参加して、楽しく料理を作っています。
和食、洋食、スウィーツ、中華、とホテルコンコルド各部門の料理長が、
ユーモアを交えて、丁寧に教えてくれます。
今回は洋食で、さつまいものクリームスープを作りました。
料理長から「スープのベースを作れば、応用できる」とアドバイスをもらいさっそく、自宅でニンジンのスープを作ってみると、いい感じのスープが出来て、感激しました。
最近は、時短レシピなど、とにかく簡単に手早く作る事ばかり注目されますが、毎日は無理でも、休日の時間に余裕のある時に、手間暇かけてじっくりと料理を作ってみては、いかがでしょうか。新しい自分に出会えるかも?
料理を作る時間も含めて、食事の時間を大切にし、何を食べるかも大切ですが、「誰と楽しく食べるか」がもっと大切だと感じるこの頃です。
一生涯のうち、あと何回、食事をするのか考えた事ありますか?
意外と、少ないですよ。
By石塚
これからの季節、ホウレン草は栄養満点!
ホウレン草の旬は、これから寒くなって行くこの季節です。
夏に比べると、ビタミンCの量や甘みも格段に上がります。
ところで、根の赤い部分、捨てていませんか?
昔は「食べてはいけない」と言われていましたが、実はここが、すごく大切な部分だったんです。
貧血を防ぐ鉄分や骨をつくるマンガンは、葉より根の赤い部分に多く含まれ、ポリフェノールも入って、栄養満点です。
そこで、料理をするのにちょっと面倒なのが、根元にたまった土を取り除くこと。ここで、ひと手間をかけて下さい。
まず根に十文字の切り込みを入れて、流水で、ていねいにもむように土を落とします。
そして、茹でたらすぐ、水にさらしてアクを抜きます。
お浸しもいいですが、油と一緒にとると、栄養の吸収がよく、バターソテーや炒め物にするのもおいしいです。
根も食べれば、生ゴミも減りますし、栄養もしっかりとれて一石二鳥です。
ちなみに、ホウレン草は英語でspinach(スピナック)です。
By石塚
みかんの季節、到来です。
みかんは冬の果物と思われがちですが、もうみかんの季節は始まっています。
今、店頭には、極早生みかんが並んでいます。少し青いので心配にはなりますが、近年、土壌改良・品質改良が進み、酸っぱさと甘さのバランスのとれた味になっています。
皮が薄く、むいた時に柑橘系の香りが広がり食欲をそそります。
極早生に始まり早生へ10月下旬からは中生(なかて)そして11月下旬からは晩生(おくて)、三ヶ日の青島みかんへ味の変化も楽しめます。
浜松の「ゆら早生」の出荷が新聞記事になっていてそろそろ店頭に並ぶ日も近いと思います。期待して下さいね。
10月から年末、正月に向けて食卓を彩るみかんを、たくさん食べて、元気にお過ごし下さい。
By石塚
はじめまして、ビアンカンスタッフの石塚です。
この場をお借りして野菜や果物のこと、食に関すること日々の生活の中で気になったことを書いていきたいと思います。
ビアンカンでの仕事は野菜などの食材を飲食店に納める仕事です。
この7月からは夜6時から8時の閉店まで、レジに立つ事もあります。
人前に出る仕事はまだまだ慣れないので口角を上げて頑張っています。
見かけたら気軽に声をかけて下さい。
よろしくお願いします。By石塚
-自己紹介-です。
・野菜ソムリエの資格を持っています。
・マイボール、マイシューズでボーリングをやっています。(ベストスコアは300点です。)
・献血回数は278回(この20数年間月1ペースで、目標は300回!)
プロフィール
前職は歯科技工士として、歯科医院、歯科技工所で30年、入れ歯を作っていました。縁あって、石原やへ。
最初は、石原農園で野菜を栽培していました。品目としては、トマト、きゅうり、枝豆、サツマイモなど。メインで栽培していたのが、白ネギです。農園の閉園にともなって、ビアンカンへ。
野菜などの食材を飲食店へ納める仕事をしています。そして、現在は夕方から、レジ業務も行っています。野菜ソムリエプロ(グリーンのスカーフです。)の資格も持っています。
趣味は、マイボウル、マイシューズで、ボーリングを、もう20年やってます。ベストスコアは、300点(パーフェクト)です。
野菜や果物のこと、食に関すること、日々の生活の中で気になったことを書いて行きたいと思います。
土づくりの開始です。2015
カテゴリ一覧
- ていねいに暮らす [402]
- ズッキーニ [3]
- コンパニオンプランツ [4]
- 自然菜園 [7]
- 育苗 [4]
- 店舗情報 [1]
- ニラ [1]
- ラディッシュ [1]
- さつまいも [3]
- ごぼう [1]
- きぬさや・スナックえんどう [3]
- 野草 [2]
- ゴーヤ [2]
- 西瓜 [8]
- 落花生 [6]
- わけぎ [3]
- 赤しそ [1]
- ★就農者募集★ [1]
- モロヘイヤ [30]
- 病害虫 [21]
- 農業体験 [10]
- 野沢菜 [10]
- その他 [28]
- 畑全体 [26]
- マスメディア [2]
- 肥料 [4]
- とうもろこし [10]
- 九条ねぎ [11]
- 生産状況 [2]
- KTC農園 [37]
- 作業の効率化 [3]
- 堆肥 [6]
- キャベツ [3]
- インゲン [3]
- オクラ [60]
- レタス [5]
- 白菜 [29]
- 緑肥(ヘアリーベッチ) [4]
- 玉ねぎ [15]
- ブロッコリー [2]
- ほうれん草 [47]
- かぶ [10]
- 大根 [35]
- 農機具 [14]
- 農資材 [12]
- 生姜 [9]
- にんじん [58]
- 自然体験 [1]
- 出荷状況 [2]
- 有機農業の生き物 [13]
- えび芋 [22]
- とまと [36]
- 緑肥(ソルゴー) [30]
- 北遠 開拓 [29]
- にんにく [11]
- 大塚 圃場の様子 [30]
- 雑感 [3]
- 緑肥(マルチ麦) [5]
- パプリカ [1]
- トウガラシ [4]
- なす [63]
- 研修やセミナー [15]
- 南瓜 [19]
- 緑肥(エンバク) [43]
- 朝市 [4]
- じゃがいも [19]
- 白ねぎ [132]
- ピーマン [6]
- 枝豆 [21]
- きゅうり [25]
- 葉ネギ [16]
- 豊岡 圃場の様子 [65]
- 今週の一枚カテゴリを追加 [4]